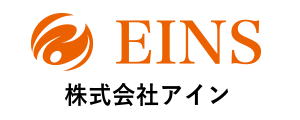機械浴とは?対象者から種類や選び方を解説

介護の現場で働く方又利用する方にとって、入浴介助は切っても切れない関係です。
では、機械浴とは一体どんなものなのでしょうか。
機械浴とは
機械浴とは、特殊浴槽やハーバード浴と呼ばれることもあり、
座った姿勢が保持できない方や寝たきりの方が使用するための浴槽です。
特別養護老人ホームや老人保健施設、介護付き有料老人ホームなどに多く設置されています。
本文に記載した「座った姿勢が保持できない方や寝たきりの方が使用するための浴槽」
こちらの内容については、文末にて改めて解説していきます。
機械浴の種類
機械浴には大きく分けてチェアー浴とストレッチャー浴があります。
< チェアー浴 >
チェアー浴とは、キャスターが付いた専用の椅子に座った状態で入浴する方法です。
浴槽をまたぐ動作が困難であっても、背もたれがあれば座位を保持できる方が対象です。
浴槽の壁が開き、椅子ごと浴槽に入るタイプで、安定感があります。
メリットは、要介護者が周囲を見渡すことができるため、安心して入浴することが可能です。
要介護者が手を動かすことができれば、タオルやスポンジを持って手の届く範囲で身体を洗うことが出来るため、自立支援にもつながります。
しかし、ストレッチャー浴と同様、金属音や機械の動作音、または移動時の振動を、利用者が不快に感じる可能性があります。また、家庭の浴槽とは違うため、利用者にとっては馴染みにくい入浴方法となるのがデメリットです。
さらに、座位が不安定な方は特に浴槽の中で身体が傾いてしまう可能性があるので、安全のために利用者にベルトを着用して、常に目を離さないようにすることが必要です。
また、介助を進めるときは必ず声掛けを行い、次に何を行うのかを説明することが大切です。
< ストレッチャー浴 >
ストレッチャーに寝たままの状態で入浴する方法です。
座位を保つことが困難な方や寝たきりの方などが対象です。
これは、ストレッチャーが昇降し担架部分をスライドさせるタイプです。
体を洗ったり、着替えを行うことができます。
メリットは、要介護者の臀部や背部など普段見えにくい場所も細かくチェックできます。
そのため、傷や皮膚トラブルの発見などにもつながります。
デメリットは、全介助での入浴となるため、利用者の意見が反映されにくく、身体機能を活かすことができません。
また、利用者にとっては寝ている状態での入浴となるため、天井以外の景色が見えづらく、さらに金属音や機械の動作音が伴うことで不快になることがあります。
そのほか、体が浮力の影響を受けやすく不安定になりやすい入浴となります。よって安全のためにベルトは必ず着用し、一つひとつの動作に入る前に、必ず利用者に伝わるように丁寧な声掛けをしてください。
機械浴を使う対象者
座位保持が困難な方
一般の家庭で使われているような浴槽では、湯船に沈んでしまう方、一般の入浴用の椅子に座っていることが難しい方などが対象です。
浴槽をまたぐ動作が困難な方
足をあげて浴槽をまたぐことが難しい方などが対象です。
寝たきりの方
身体を自由に動かすことが出来ず、日中もベッドの上で過ごす方などが対象です。
骨折したばかりで身体を動かすことが困難な方
転倒して骨折したり、同じ姿勢を続けて圧迫骨折をしたりしたばかりで、安静を必要とする方などが対象です。
入浴介護にどれだけスペースをとれるか
介護浴槽には大型/小型浴槽があります。
大型浴槽 横幅(入口)4500mm × 縦(奥行)3500mm
【メリット】
浴槽内寸が大きいため、ゆったり入浴できる。
大柄なご利用者や姿勢制限のある方でも入浴しやすい。
【デメリット】
より設置スペースを必要とする。
小型浴槽 横幅(入口)4000mm × 縦(奥行)3000mm
【メリット】
コンパクトに設置できるため、スペースに余裕のない時に適している。
【デメリット】
浴槽内寸が比較的小さいため大柄な方や姿勢制限のある
ご利用者の入浴には不向き。
最も解決したい課題は何か、整理する。
上記のポイントの他にも、予算や設備条件などのさまざまな検討要素があり、すべての条件を満たせないこともあります。
(例)寝た姿勢であればより重度の方が入浴できるが、より多くの設置スペースが必要なる、等
一番大切な事は、導入により解決したい課題は何かを振り返り、優先順位づけをすることです。
座った姿勢が保持できない方や寝たきりの方が使用するための浴槽
文頭に書かせていただきました、内容について解説していきます。
機械浴を使う上で、スペースの確保を初め予算面・設備条件等、導入時に事前に確保しておかなければ
いけない事が複数あげられます。
その中でも、スペースの確保・設備条件です。
各施設の建て方や設備は、同じ条件で建てられているところは少ないのではないでしょうか?
ましてや、自宅での場合は想像がしにくいのではないでしょうか?
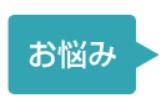
場所が確保できない・設備(配管工事)= 費用 が負担になる
体が温まらず、体を拭いている間に足が冷えてしまう、、、
主なご意見を、一部抜粋させていただきました。
今回、掲げたようなお悩みから
介護される側・介護する側 双方立場に立ち入浴装置を開発いたしました。
ナノミストバスは機器が移動ができ、設備(配管工事不要)
①電源→家庭用コンセント(100V)
②水→1人/ペットボトル約1本(約330ml)
+プラス
体を洗う必要なし(洗剤使用なし)
<ナノミストバス製品ラインナップ>
ナノミストバスベッド・ナノミストバスキャリー・ナノミストバス2way・ナノミストバスフットスパ
ナノミストバスキャビンS・ナノミストバスシェル・ヘッドスパ
ナノミストバス災害用
<ナノミストバスとは>
ナノミストバスは湯船に浸からない新しいお風呂です。38℃~42℃の室温を保ちドライサウナのような息苦しさが無くサウナが苦手な方や高齢の方など、どなたでも心身ともにリラックスできます。リラックスした全身ナノ浴は優れた保温効果があり、入浴後はモイスチャー効果で、角質層に十分な水分を与え、乾燥によるかゆみを軽減でき、全身を包んだナノ粒子が体を芯から温めポカポカ感が続きます。
詳しくは、EINS(アイン)ホームページにも記載しております。
ぜひ、ご覧ください。
今回の記事では「 介護ベッド と 入浴」の関係性にて書かせていただきました。
この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。